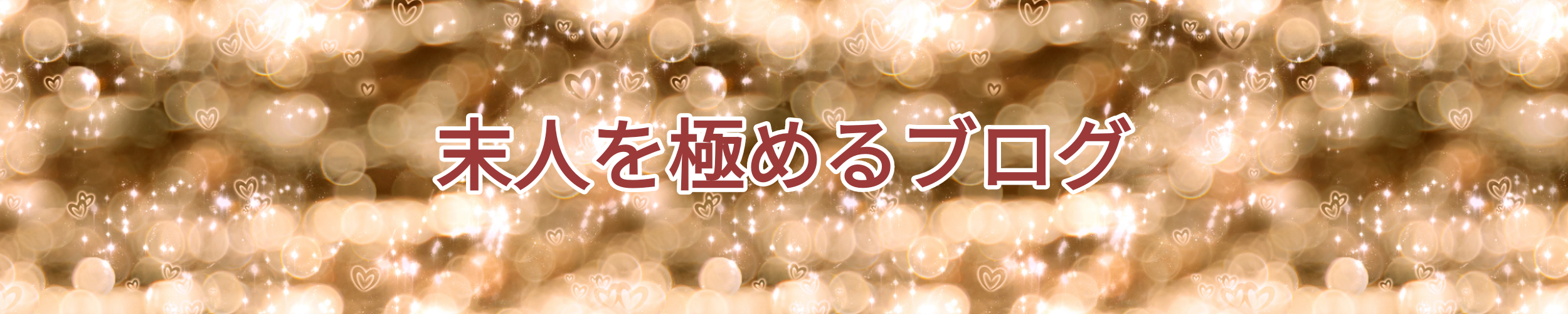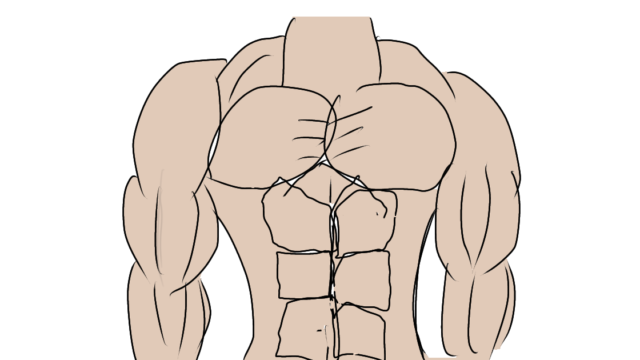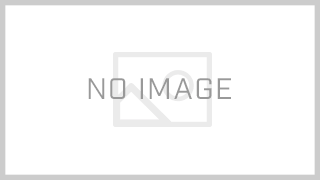メラビアンの法則は有名ですが、少し誤解を孕んでいるなと感じましたので共有します。
メラビアンの法則とは
①言語情報が7%、聴覚情報が38%、視覚情報が55%の割合で影響を与える
②言葉と表情に統合性が取れない場合は、言葉よりも表情を優先する
③言語情報と聴覚情報が矛盾すると、聴覚情報を優先して解釈する傾向がある
よく本などで取り上げられるのは①の部分になり、
言語情報よりも聴覚情報や資格情報の方が与える影響が大きいという理由から
・コミュニケーションは表情が大事なので笑顔でしよう、
・コミュニケーションはジェスチャーをいれよう
・本では相手が分からないから、実際にメンターにあってみよう
・本よりも動画のほうが情報量が多い
こういった結論を導き出していることが多いです。
導き出した結論は間違ってはいないですが、数字ほどは大差はないです。
「言葉と表情に統合性が取れない場合」が抜けている
メラビアンの法則は、言葉と表情に統合性が取れない場合の実験です。
笑顔で「死ね」と言われたときに、どっちの印象を強く受けましたか?という実験ですね
これは例えばですども
すごく迷惑そうな顔と声で「ありがとう」といったとき、「ありがとう」という言葉の意味をそのまま受け取ったのか?それとも嫌な感じを受けたのか?
そりゃあ、普通の感覚の持ち主なら感謝されてないなと思いますよね。
先程もいいましたが、だからといって結論が間違っていることはなく。
コミュニケーションは元気に笑顔で行ったほうがいいし、文字情報よりも視覚情報のある動画や実際に会ってみたほうが、その人のことがよく分かるというのは、その通りです。
普通のコミュニケーションでは、数字ほどのインパクトはないよというのは覚えておきましょう。
曲解して、言語情報は7%しか意味ないから、適当なこと話してもいいやとはならないように。